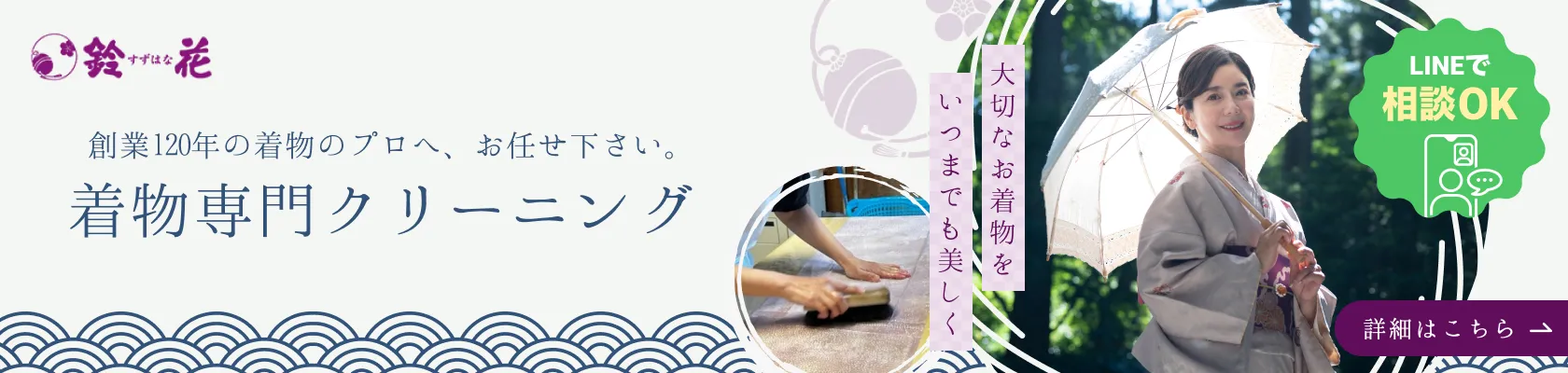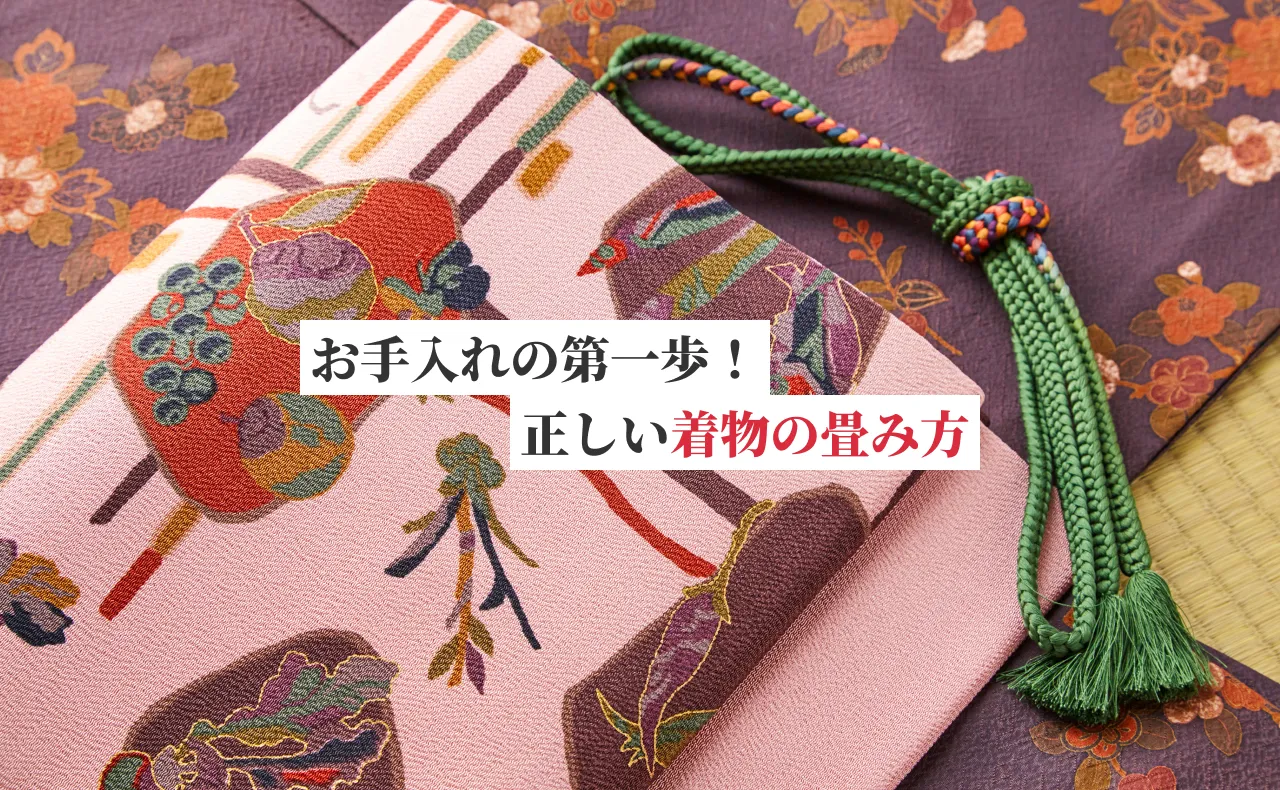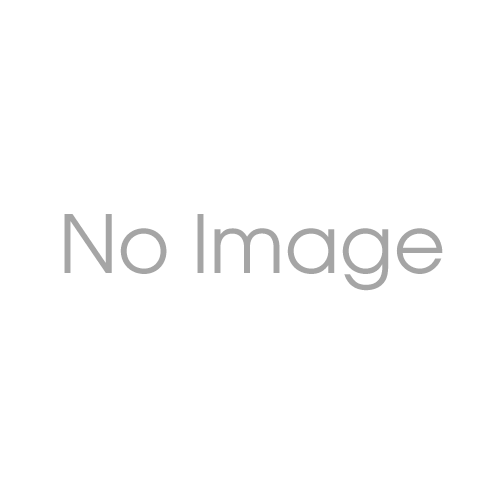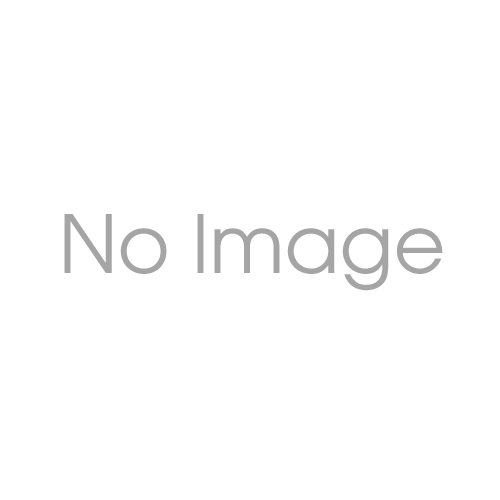最終更新日:
記事公開日:
着物を収納・保管する上での基本や注意点についてくわしく解説
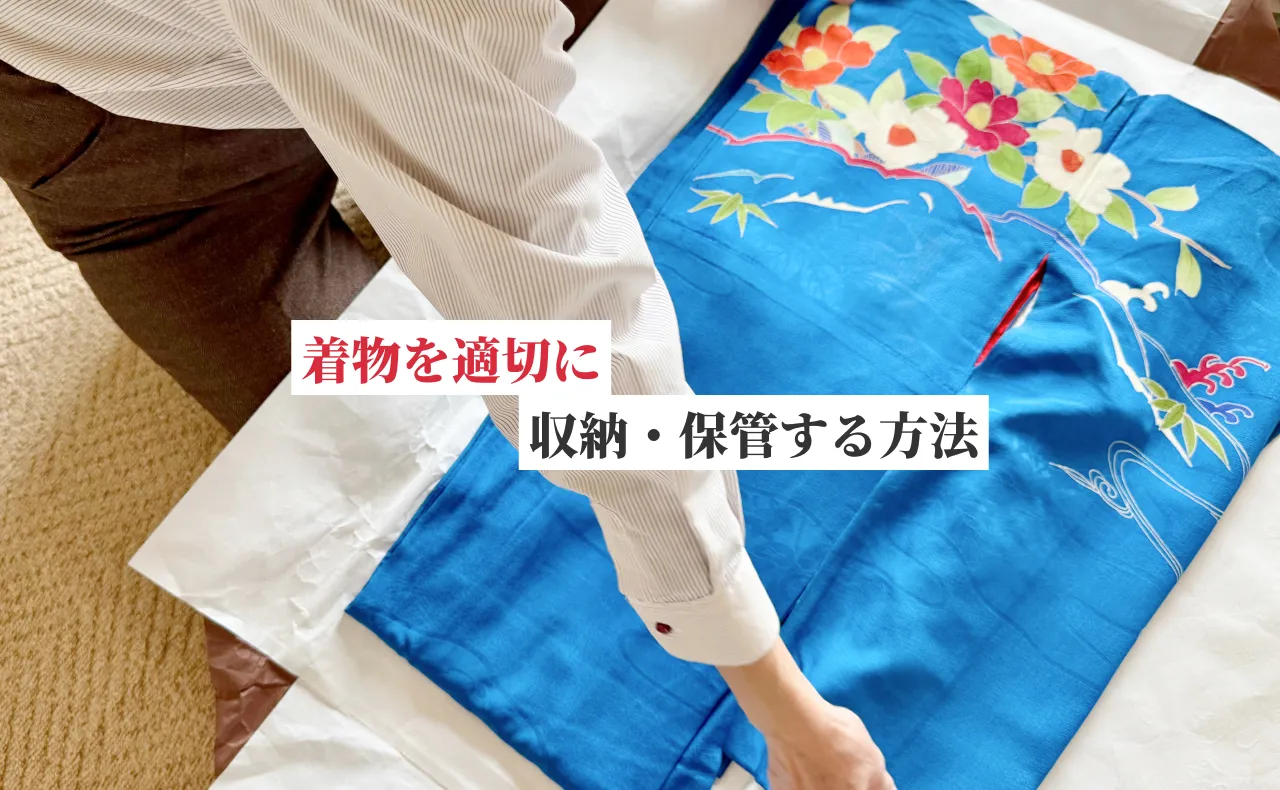
繊細な素材で作られている着物は、適切な方法で保管しなければすぐに傷んでしまいます。とくに汚れや湿気が残ったまま収納してしまうと、カビや変色などが発生してしまうため注意が必要です。
とはいえ、普段からよく着物を着ているわけではない場合は、「着物を収納する方法がよくわからない」「着物を収納する前に行うべき手入れを知りたい」と感じるケースも多いのではないでしょうか。
そこで本記事では、着物を収納するときの基本的なポイントや注意点、収納ケースなどについて解説します。着物の収納方法を知りたい方は、ぜひ参考にしてみてください。
着物を収納・保管する上での基本
着物は繊細な素材で作られており、湿気や直射日光、虫害などによって劣化しやすいため、適切な収納・保管が不可欠です。長く美しい状態を保つためには、着物の特性を理解し、保管環境や取り扱いに細心の注意を払う必要があります。
基本的な着物の収納・保管の原則は、以下の4点です。
- 湿気を避ける
- 風通しを良くする
- 直射日光を当てない
- 清潔な状態でしまう
これらを守ることで、カビや変色、虫食いなどのトラブルを防げます。また、着物の生地や仕立て、用途によって保管方法を工夫することも大切です。
保管場所には桐たんすが最適とされており、湿度の調整機能や防虫効果が期待できます。ただし、現代の住宅事情によりプラスチックケースなどの代用も増えています。どの収納方法を選ぶにしても、通気性と湿気対策を意識することが着物を守るための基本です。
着物を収納する前にやるべきこと
着物を収納する前にやるべきこととして、以下の3つのポイントを紹介します。
- 汚れがないか確認する
- 日陰で干し汗を飛ばす
- しわなく畳みたとう紙で包む
汚れがないか確認する
着用後は必ず着物全体の汚れやシミを確認しましょう。衿元や袖口、裾などはとくに汚れやすい部位です。目立つ汚れがある場合は、専門のクリーニング店に依頼するのが望ましいでしょう。軽い汚れやホコリ程度であれば、柔らかいブラシや乾いた布で優しく払い落とすだけでも効果的です。
また、汗による見えない汚れが繊維に残ると、変色やカビの原因になります。外観に問題がなくても、着用時間が長かった場合や汗をかいたと感じた場合は、陰干しを行いましょう。
日陰で干し汗を飛ばす
着物に限らず和装品全般にいえることですが、収納前には必ず風通しのよい日陰で陰干しをして、湿気を取り除く必要があります。直射日光に当てると色あせや繊維の劣化が起こるため、室内の風通しのよい場所か、カーテン越しの柔らかい光が当たる場所で干すのが理想です。
陰干しは着物を裏返し、袖を広げて行うのが基本です。1〜2時間程度風に当てるだけでも十分に湿気を飛ばせます。干しすぎると乾燥しすぎて生地がパリパリになることがあるため、適度な時間を意識しましょう。
しわなく畳みたとう紙で包む
陰干しの後は、着物を丁寧に畳み、「たとう紙」に包んで収納します。たとう紙とは、通気性に優れた和紙でできた包み紙で、着物を湿気や汚れから守る役割を果たします。市販のたとう紙でも問題ありませんが、古くなったものは湿気を吸っている可能性があるため、定期的に新しいものと交換するのがおすすめです。
畳む際には、しわが入らないように注意し、決められた畳み方に従って丁寧に作業しましょう。着物の種類(振袖・訪問着・留袖など)によって畳み方が異なる場合があるため、正しい方法を確認することが大切です。
着物を収納するときの注意点
ここでは、着物を収納するときの主な注意点として、以下の2点を解説します。
- 着物を詰め込まない
- 定期的に着物に風を通す
着物を詰め込まない
収納スペースに着物を詰め込みすぎると、通気性が悪くなり、湿気がこもってカビや虫の発生につながります。また、重なりすぎると生地にしわがついたり、型崩れの原因にもなるため注意が必要です。
収納する際は、1枚1枚の着物の間に余裕を持たせ、たとう紙ごとに重ねても3〜5枚程度にとどめるのが理想です。スペースに余裕がない場合は、収納ケースを増やす、または季節ごとに入れ替えるなどして調整しましょう。
定期的に着物に風を通す
着物はたとえ一度も着ていなくても、収納中に湿気を含むことがあります。年に2〜3回は収納場所を開けて中の空気を入れ替え、必要に応じてたとう紙を開いて着物にも風を通しましょう。
着物に風を通す作業は、梅雨明けや秋口の湿度が落ち着いた晴れの日に行うのがベストです。風を通すだけでなく、防虫剤や除湿剤の交換もこのタイミングで行うとよいでしょう。なお、防虫剤と除湿剤は一緒に使うと化学反応を起こす場合があるため、併用する際は製品の注意書きをよく確認してください。
着物の収納におすすめのケースの種類
着物の収納におすすめのケースとして、たんす・プラスチックケースの2つを紹介します。
たんす
着物の収納には、たんすがおすすめです。とくに桐たんすは調湿性と防虫性が高く、着物収納に最も適した伝統的な家具として知られています。桐は湿度が高いときには湿気を吸収し、乾燥時には放出するという性質を持っており、着物を湿気から守る理想的な素材です。また、桐材には虫が嫌う成分も含まれているため、防虫剤を使わなくてもある程度の防虫効果が期待できます。
桐たんすは高価なものが多いものの、長期的に着物を保管する予定がある方や、本格的な和装をする方にとっては一度購入する価値があります。たんすの中は着物用に設計されているため、たとう紙に包んだ着物を重ねて入れやすく、しわや型崩れのリスクも低減可能です。
プラスチックケース
収納スペースに制限がある方や、リーズナブルに着物を保管したい方には、プラスチック製の収納ケースもおすすめです。近年では着物用に設計された専用のケースも販売されており、通気口が付いていたり、湿気対策用の構造が施されているものもあります。
ただし、通気性は桐たんすに劣るため、除湿剤や防虫剤を併用する必要があります。また、密閉性が高いものが多く、湿気がこもりやすくなるリスクもあるので、定期的な風通しが必須です。
選ぶ際には、サイズや積み重ねの可否、取り出しやすさを重視しましょう。中が見える透明タイプであれば、どの着物が入っているか一目でわかり、取り出しもスムーズになります。
プラスチックケースは、予算や収納スペースに制限がある人でも気軽に導入できる点が魅力ですが、着物の品質を保つためには、通気性・湿度管理を徹底する必要があります。
まとめ
本記事では、着物を収納する際の基本的なポイントや注意点、収納に適したケースなどについて解説しました。着物を収納するときは、汚れや湿気を取り除いたうえで、しわなくきれいに畳み、たとう紙に包んで収納しましょう。
ケースに着物を入れる際は詰め込みすぎないのもポイントです。また、湿気がこもらないように定期的に風を通しましょう。着物を収納するケースとしては、たんすやプラスチックケースがおすすめです。とくに桐たんすは調質性・防虫性に優れており、着物の収納に適しています。
鈴花グループでは、九州・中国・四国地方を中心に、着物をはじめとした女性のファッションを提案しています。着物の洗い~収納までトータルでの手入れサービスも提供しているので、着物の洗濯や収納にお困りの方はぜひ当グループにご相談ください。
鈴花グループの詳細はこちら
ライター紹介