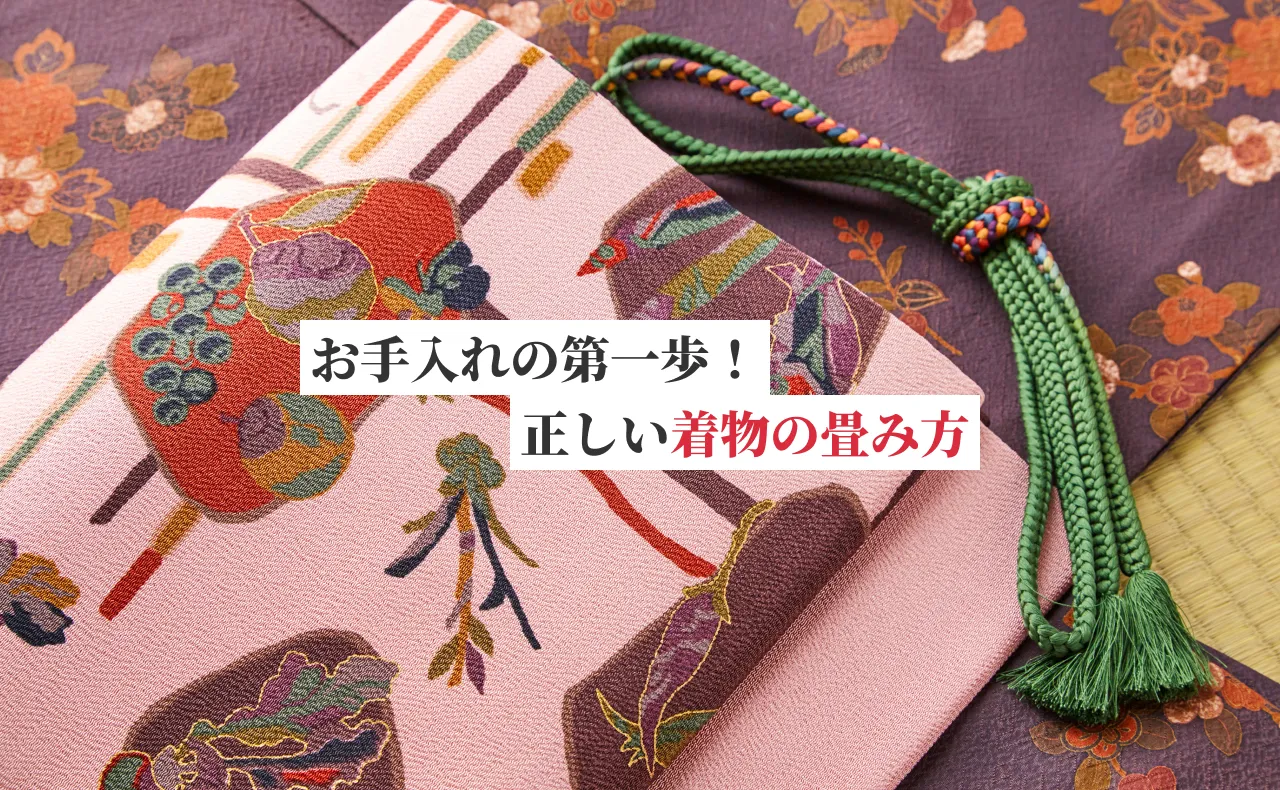記事公開日:
付け下げとは?着用シーンや訪問着・色無地との違いを解説

付け下げは、訪問着に次ぐ格の準礼装として位置づけられる着物です。派手すぎず、ある程度の格式が求められるシーンに適しています。
ただ、付け下げと似た着物は多いため、「付け下げはどんなときに着るの?」「付け下げと訪問着・色無地の違いは?」と疑問に感じている人もいるのではないでしょうか。
そこで本記事では、付け下げとは何か、着用シーンやほかの着物との違いについて解説します。着物選びで付け下げを検討している場合は、ぜひ参考にしてみてください。
付け下げとは
付け下げ(つけさげ)とは、訪問着に次ぐ準礼装として位置づけられる着物の一種です。
模様が縫い目をまたがずに配置されているのが特徴で、柄が上向きにデザインされているため、着用した際に模様が自然と美しく見えるよう工夫されています。
もともと付け下げは、訪問着よりも手軽に楽しめる着物として登場しました。訪問着は一度反物を仮仕立てして模様を描いた後に本仕立てするため手間がかかりますが、付け下げはそのまま反物の状態で模様を染めることが可能です。そのため制作工程が簡略化され、価格も比較的抑えられています。
そのため、訪問着に比べて控えめながらも上品な印象があり、フォーマルにもセミフォーマルにも対応できる万能な着物として多くの女性に親しまれています。模様の配置や色合いも落ち着いたものが多く、派手すぎず、それでいてきちんとした装いが求められる場面にぴったりの着物です。
付け下げの着用シーン
付け下げはその品のよさと適度な格式から、幅広いシーンで着用できます。付け下げの主な着用シーンを5つ紹介します。
親族や友人の結婚式
付け下げは、結婚式にゲストとして出席する際の装いにおすすめの着物です。訪問着ほど華やかすぎず、色留袖のようにかしこまりすぎない絶妙なバランスが、親族や友人としての立場にふさわしい印象を与えます。
落ち着いた色味や上品な柄の付け下げを選べば、新郎新婦を引き立てつつ、自身も礼儀正しい装いとして映えるでしょう。既婚・未婚を問わず着用でき、帯や小物で華やかさを加えることで、お祝いの気持ちを表現することができます。
子どもの入学式・卒業式
入学式や卒業式といった子どもの大切な節目の場では、母親の服装にも品位と格式が求められます。付け下げは、そうしたシーンで控えめながらも華やかさを演出できる装いとして人気です。
訪問着よりも落ち着いた印象があり、派手になりすぎず、学校行事という場にも調和します。パステル系やベージュ、淡いグレーなどの明るく清潔感のある色を選ぶと、式典の雰囲気にもよく合うでしょう。
七五三やお宮参りなど家族の行事
七五三やお宮参りなど、子どもの成長を祝う家族行事でも付け下げは重宝されます。母親として品よく見せたい一方で、主役である子どもを引き立てたいという場面で、控えめな華やかさの付け下げがちょうどよい選択肢となるでしょう。
こうした行事では、淡いピンクや薄紫、若草色などの優しい色味が好まれます。帯や小物に季節感を取り入れることで、記念写真にも映える装いが可能です。
パーティーや会食、茶会
格式が高すぎないフォーマルな場、たとえばパーティーや会食、茶会などでも、付け下げは活躍します。訪問着ほど主張せず、それでいてTPOをわきまえた品格を持つ装いとして、場の雰囲気を壊すことなく溶け込むことが可能です。
茶会などでは派手すぎない落ち着いた模様や色合いが求められるため、付け下げの控えめな柄は理想的です。帯の色や結び方を変えることで、シーンに応じた変化をつけることもできます。
観劇や初詣など少し改まったお出かけ
観劇や初詣など、日常より少しだけ改まった装いをしたい場面にも、付け下げはぴったりです。とくに観劇では周囲とのバランスを取りつつ、品よく華やかに見せる装いが好まれます。
初詣では新年の清々しい気持ちを表す淡色系の付け下げが人気で、防寒対策として羽織やショールを加えても雰囲気を壊しません。
付け下げと訪問着の違い
付け下げと訪問着の違いは、以下の表のとおりです。
| 項目 | 付け下げ | 訪問着 |
|---|---|---|
| 格 | 準礼装(訪問着よりやや格下) | 準礼装(付け下げより格上) |
| 模様の描き方 | 反物の状態で模様を染める(縫い目をまたがない) | 仮仕立てしてから模様を描く(縫い目をまたぐ) |
| 模様の位置 | 上向きに配置され、着用時に美しく見える | 全体につながる絵羽模様が特徴 |
| 見た目の豪華さ | 控えめで上品 | 華やかで豪華 |
| 着用シーン | 結婚式、入卒式、茶会など幅広く対応 | 結婚式、式典、フォーマルな集まりなど |
| 価格帯 | 比較的手頃 | 高価になりやすい |
付け下げと訪問着は見た目が非常に似ており、柄の印象も重なる部分がありますが、両者の違いは主に模様の配置方法と制作工程にあります。
訪問着は仮仕立てした状態で模様を描き、その後に本仕立てされるため、肩から裾にかけて模様が縫い目をまたいでつながる「絵羽模様(えばもよう)」が特徴です。このため、模様の一体感があり、より豪華な印象を与えます。
一方、付け下げは反物の状態のまま模様が描かれるため、縫い目をまたぐことはありませんが、模様の向きはすべて上を向いており、仕立て上がったときに美しく見えるように設計されています。模様のボリュームも訪問着よりやや控えめです。
また、訪問着の方が格式が高く、よりフォーマルな場に適しています。付け下げは、訪問着よりややカジュアルな場面で着用されることが多く、価格面でも手に取りやすいのが特徴です。
付け下げと色無地との違い
付け下げと色無地の主な違いは、以下の表のとおりです。
| 項目 | 付け下げ | 色無地 |
|---|---|---|
| 格 | 準礼装(訪問着よりやや格下) | 紋の数により略礼装〜準礼装まで対応可能 |
| 模様 | 控えめな模様あり | 無地(柄なし) |
| 着用シーン | 結婚式、入卒式、茶会など幅広く対応 | お茶会、法事、式典、慶弔行事など |
| 紋の有無 | 入れないのが一般的 | 入れることで格が上がる |
| カスタマイズ性 | 柄による変化が主 | 帯や小物で雰囲気を自由に変えられる |
色無地(いろむじ)は、文字通り一色で染められた柄のない着物で、シンプルながらも着用シーンの幅が広く、格式も紋の数によって調整できるのが特徴です。着用者の個性を控えめに引き立てる装いとして、多くの場面で重宝されます。
一方、付け下げには控えめながらも模様があり、色やデザインによって華やかさを出せるというのが主な違いです。色無地は落ち着いた装いを演出するのに適しており、茶道などの習い事やお茶会、法事、式典などで幅広く使われます。
また、色無地には家紋を入れることができ、これによって着物の格を調整できるのがポイントです。三つ紋入りの色無地は準礼装として扱われ、結婚式の親族や公式行事にも着用できます。
対して、付け下げは模様がある分、視覚的に華やかで、パーティーや結婚式、晴れの日の装いに向いています。どちらがよいというよりも、TPOや目的に応じて選ぶことが大切です。
まとめ
本記事では、付け下げとはどんな着物なのか、着用シーンや訪問着・色無地との違いなどについて解説しました。付け下げは、適度な華やかさと格式の高さから、結婚式・入学式・茶会などさまざまなシーンで着用できる着物です。派手すぎない着物を着たい場合に適しています。
鈴花グループでは、九州・中国・四国地方を中心に、着物をはじめとした女性のファッションを提案しています。付け下げも取り扱っておりますので、結婚式や入学式などのイベントに付け下げを着用したいという方は、ぜひ当グループにご相談ください。
ご興味をお持ちの方は、お近くの店舗へぜひお越しください。
店舗の一覧は下記のページよりご覧いただけます。
https://www.suzuhana.co.jp/shop/
ライター紹介