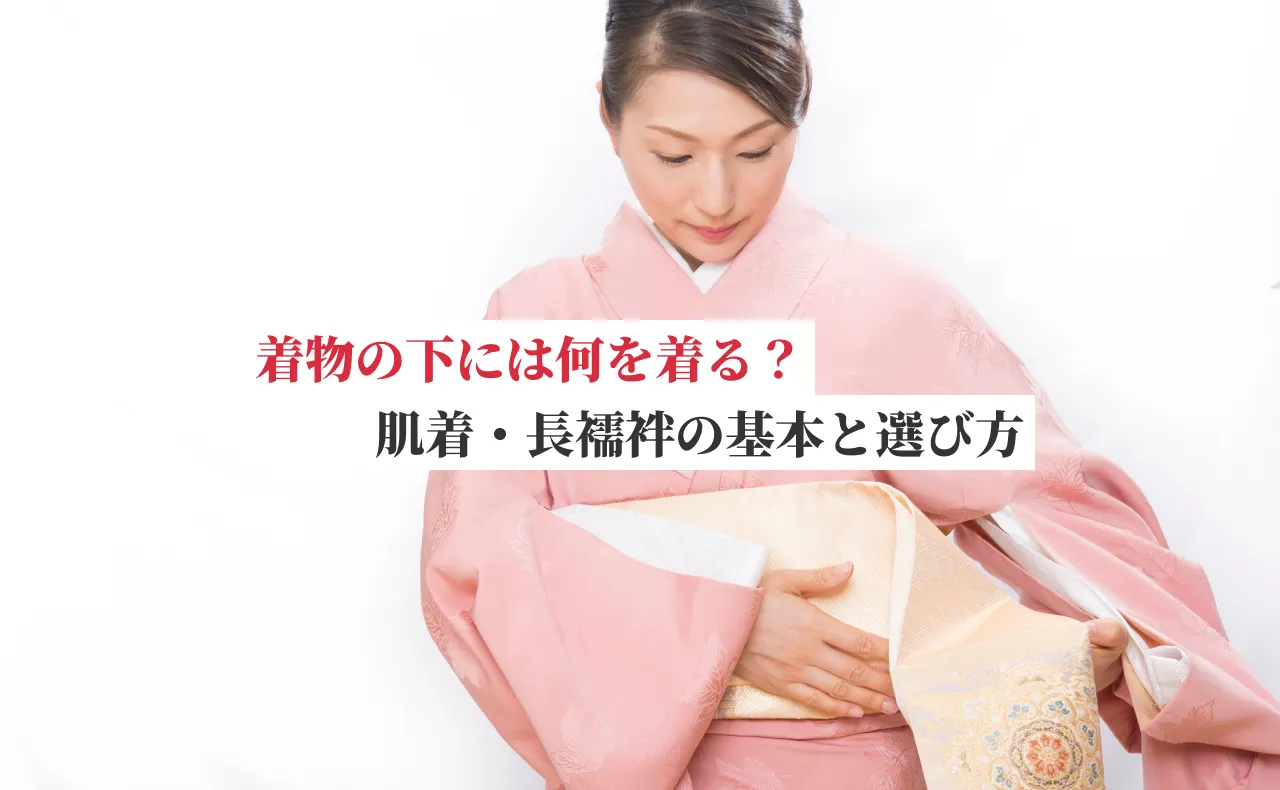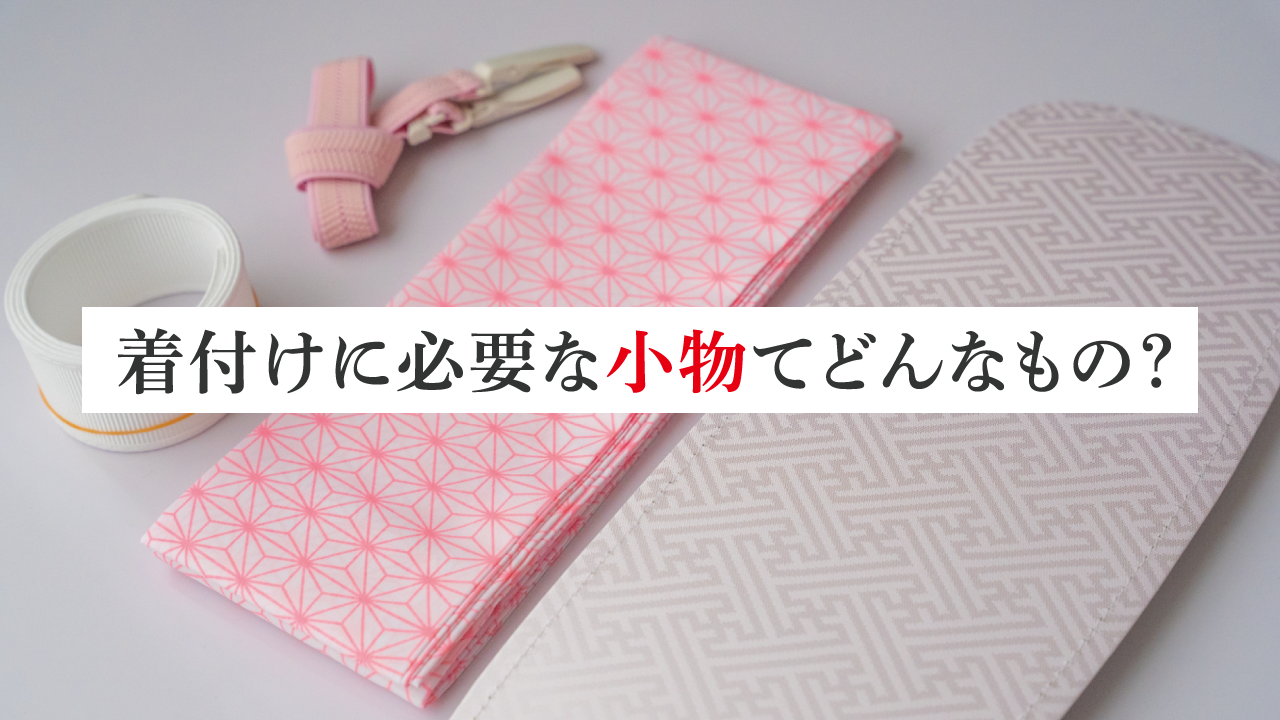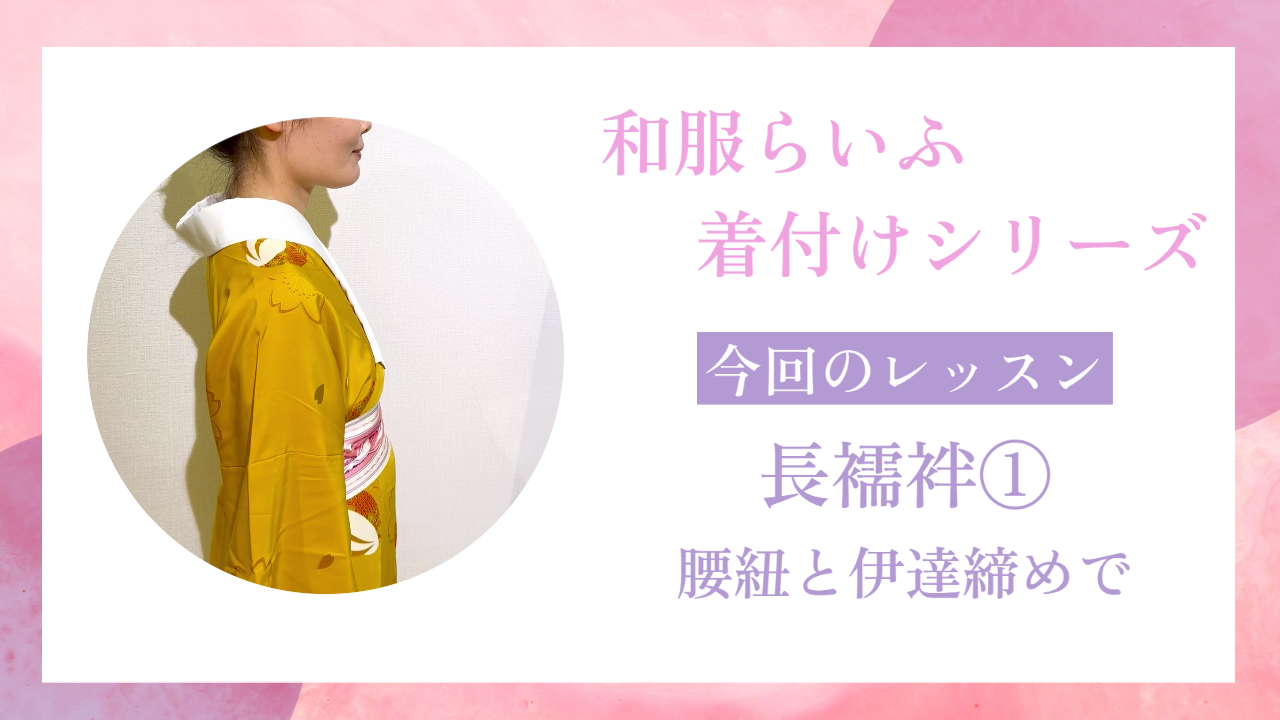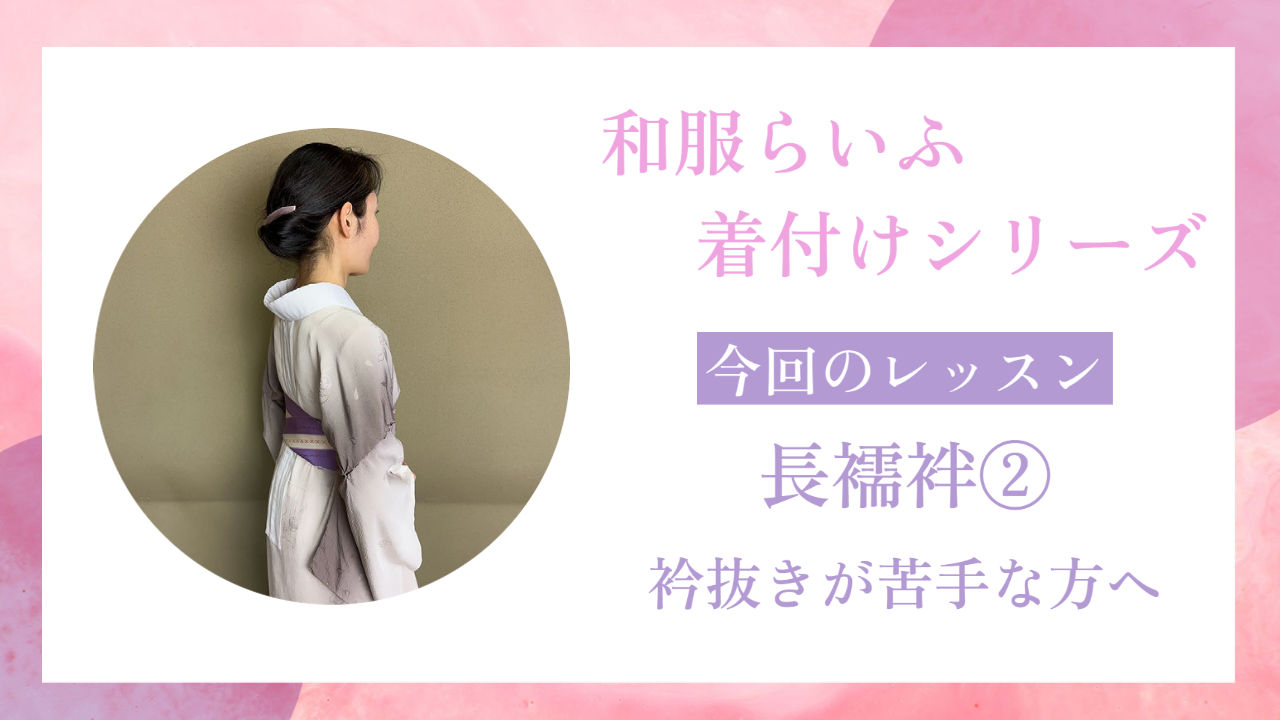最終更新日:
記事公開日:
どっちが上?着物の右前と左前について解説

着物の前合わせには正しい方向があり、間違えてしまうとマナー違反になるため注意が必要です。とくに大切な式典などの場では周囲に不快な思いをさせてしまうリスクもあるため、必ず正しい前合わせの方法を知っておきましょう。
とはいえ、普段あまり着物を着ない人には、「着物の前合わせは左右どっちが上?」「着物の右前と左前の違いは?」など疑問に感じている人も多いのではないでしょうか。
そこで本記事では、着物の正しい前合わせが右前なのか左前なのかについて解説します。正しい前合わせを忘れなくなる覚え方のコツや、着物を着る際の注意点なども紹介するので、着物の着方で困っている場合はぜひ最後までチェックしてみてください。
どっちが上?着物の右前と左前とは
着物の前合わせには「右前」と「左前」という呼び方があります。これは衿を体の前で重ねる際、どちらが上になるかを示す言葉です。右前とは自分から見て右側の衿が内側になり、その上に左側の衿を重ねる着方を指します。左前はその逆で、左の衿が内側、右の衿が上にくる状態です。
現代の洋服ではボタンやファスナーで留めるため前合わせの向きを意識する機会が少なく、初めて着物を着ると左右がわかりづらいと感じる人も多いでしょう。しかし、着物は前合わせの向きが非常に重要で、見た目だけでなく文化的・礼儀的な意味合いもあるため注意が必要です。
正しい前合わせを守ることで、美しく着こなせるだけでなく、着物を着る場面での礼を尽くすことにもつながります。
着物は右前で着るのが正しい

着物は必ず右前で着用しましょう。右前は右側の衿を体に沿わせ、その上から左側の衿を重ねることで、左衿が外側に見える着方です。右前が正しい着方であることは男女共通で、成人式や結婚式などのフォーマルな場から、浴衣や小紋といったカジュアルな着物まであらゆる場面で共通しています。
もともと日本では、着物の前合わせに明確な決まりはありませんでした。古墳時代から飛鳥時代にかけての埴輪や絵画には、衿が左右どちらでも重ねられている様子が見られ、当時は右前と左前の区別なく着られていたと考えられています。
この状況が大きく変わったのは奈良時代のことです。西暦719年、全国の人々に右前で着ることが義務づけられる法令が出されました。この法令をきっかけに、右前は貴族や役人など上層階級だけでなく、庶民の間にも浸透していったとされています。
着物を左前にしてはいけない理由
着物を左前で着るのは、亡くなった方に着せる「死装束」として用いられる着せ方にあたるため基本的に避けなければなりません。葬儀や通夜で納棺される際、故人には右の衿を上にして着せます。これは生者と死者を明確に区別するための習慣であり、長い歴史の中で定着してきました。
そのため、生きている人が左前で着物を着ると「死を連想させる」とされ、非常に縁起が悪いと考えられています。日常的な場面はもちろん、成人式や結婚式など慶事の場で左前になってしまうと、周囲に不快感や不安を与えてしまう可能性があるため要注意です。
前合わせの簡単な覚え方
着物を着る際、正しい前合わせである右前の簡単な覚え方として、以下の3つのポイントを紹介します。
- 洋服とは逆に着る
- 衿元は相手から見て「y」の形に合わせる
- 衿元は右手を入れやすいように合わせる
洋服とは逆に着る
日常的に着ている洋服は、女性用は左前、男性用は右前にボタンが付いていることが多いのに対して、着物は性別を問わず右前に合わせるのが決まりです。そのため「洋服とは逆にする」と意識すると覚えやすくなります。
とくに洋服感覚で衿を重ねると無意識に左前にしてしまう人が多いため、最初に「逆にする」と声に出して確認するのも効果的です。また、練習時にわざと洋服のボタン合わせを思い出してから反対側を上にする手順を踏むと、体に感覚として定着しやすくなるでしょう。
衿元は相手から見て「y」の形に合わせる
着物を着たとき、正面から見た衿元がアルファベットの「y」に見える形になっていれば正しい右前です。左側の衿が上にきて右側の衿が下に入り込むことで自然にy字ができます。
ただし、鏡で見ると左右が逆に映るため、自分から見た印象に惑わされやすいため要注意です。スマートフォンで写真を撮って反転表示を確認するなど、相手視点で判断しましょう。式典や行事の当日は、出かける前に家族や友人に「y字になっているか」を見てもらう習慣をつけると安心です。
衿元は右手を入れやすいように合わせる
もう1つの感覚的な方法が、衿元に右手を差し入れやすいかどうかで判断するというものです。右前で着ている場合、右手を衿元から差し込むと自然に布が開きますが、左前では右手が衿に引っかかって入りにくくなります。動作の感覚で確かめられるため、着付け中に鏡がなくてもその場で確認できます。とくに子どもや着物初心者には、感覚的に覚えやすいのでおすすめです。
着物を着た際の注意点
着物を着る際の主な注意点として、以下の5点について解説します。
- 衿元のゆるみに注意する
- 写真や鏡では左右反転に注意する
- 着崩れ防止の工夫をする
- 動作で前合わせがずれないようにする
- 周囲と協力してチェックする
とくに普段あまり着物を着ない人はしっかりチェックしておきましょう。
衿元のゆるみに注意する
着物は動作や時間の経過で衿元がゆるみやすくなります。衿が開いてしまうとだらしない印象を与えるだけでなく、礼儀を欠いた着こなしに見られてしまう可能性もあるため要注意です。
着付けの際は伊達締めや腰紐をしっかり締め、衿が浮かないように整えることが大切です。出かける前に鏡で衿元の密着具合を確認し、緩んでいたらすぐに直す習慣をつけましょう。
なお、長襦袢や浴衣の着付けの方法については、以下の記事で詳しく解説しています。具体的な着付け方の手順について知りたい場合は、ぜひ参考にしてみてください。
写真や鏡では左右反転に注意する
鏡で見たときに左右が反転して映るため、自分では右前と思っていても実際は左前になっていることがあります。また、スマートフォンのインカメラも初期設定では左右反転していることが多いため注意が必要です。
写真を撮ったら反転表示にして確認したり、できればほかの人にチェックしてもらったりとチェックを徹底しましょう。とくに式典や人前に出る機会では、出発前に正しい前合わせになっているか第三者の目で見てもらうと安心できます。
着崩れ防止の工夫をする
帯や腰紐が緩むと着物全体のバランスが崩れやすくなります。動きやすさを優先して緩めに結ぶと、立ち座りの動作で一気に着崩れる恐れがあるため注意が必要です。
長時間の外出や行事の際は、腰紐などを使って固定力を高めると安心です。定期的に鏡で姿を確認し、崩れてきたと感じたら早めに直すように心がけましょう。
動作で前合わせがずれないようにする
座る・立つなどの日常動作でも、着物の前合わせはずれやすいものです。とくに座る際に裾を踏んだり引っ張ったりすると、衿が引きつれてずれてしまうことがあります。
動作のたびに裾を軽く持ち上げて体の動きを妨げないようにすると、衿元への負担が減り着崩れを防ぐことが可能です。正しい姿勢を意識することもずれ防止に効果的なので、背筋を伸ばして座る・立つ習慣をつけるとよいでしょう。
着物を着たときの座り方・立ち方・歩き方については、以下の記事で詳しく解説しています。正しい動作について確認したい場合は、ぜひあわせて参考にしてみてください。
周囲と協力してチェックする
着物に不慣れなうちは、自分だけで前合わせや衿元の状態を完全に管理するのは難しい場合があります。外出先で気づかないうちに衿がずれていることもあるため、家族や友人と互いにチェックし合う習慣をつけると安心です。
人から見てもらうことで、鏡では見えにくい後ろ姿や帯の傾きも確認できます。とくに式典など大勢の前に出る場面では、出発直前や会場到着後に必ず確認してもらいましょう。
まとめ
この記事では、正しい着物の前合わせについて解説しました。着物を着る際の前合わせは必ず右前にしましょう。右前は、自分から見て右側の衿が内側になり、その上に左側の衿を重ねる着方です。左前は亡くなった方に着せる「死装束」として用いられる着せ方であり、マナー違反となるため注意してください。
着物を右前で着るためには、「洋服とは逆に着る(女性の場合)」「衿元は相手から見て『y』の形になるように着る」「衿元は右手を入れやすいように着る」などのポイントを覚えておくと間違えにくいでしょう。大切な式典などに出席する際は、第三者のチェックを受けると安心です。
鈴花グループでは、九州・中国・四国地方を中心に、伝統的な着物から現代的な女性ファッションまで、あなたらしいスタイルをご提案しています。
「着物に興味はあるけれど、着方がわからない…」 「一人で着付けるのは不安…」
そんなお悩みをお持ちの方も、経験豊富なスタッフが、着物の基本的な着方から丁寧にお教えします。着付けサービスも承っておりますので、特別な日にも安心してお任せいただけます。
ご興味をお持ちの方は、お近くの店舗へぜひお越しください。
店舗の一覧は下記のページよりご覧いただけます。
https://www.suzuhana.co.jp/shop/
ライター紹介