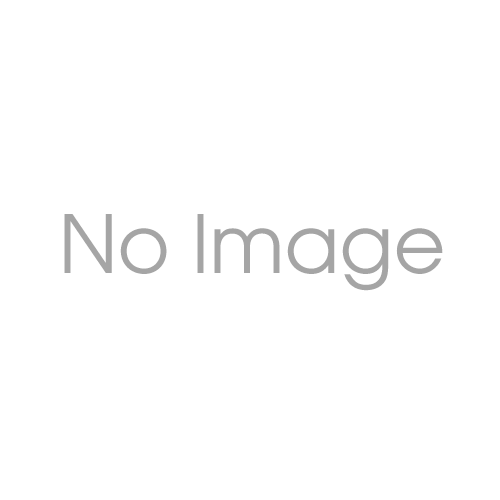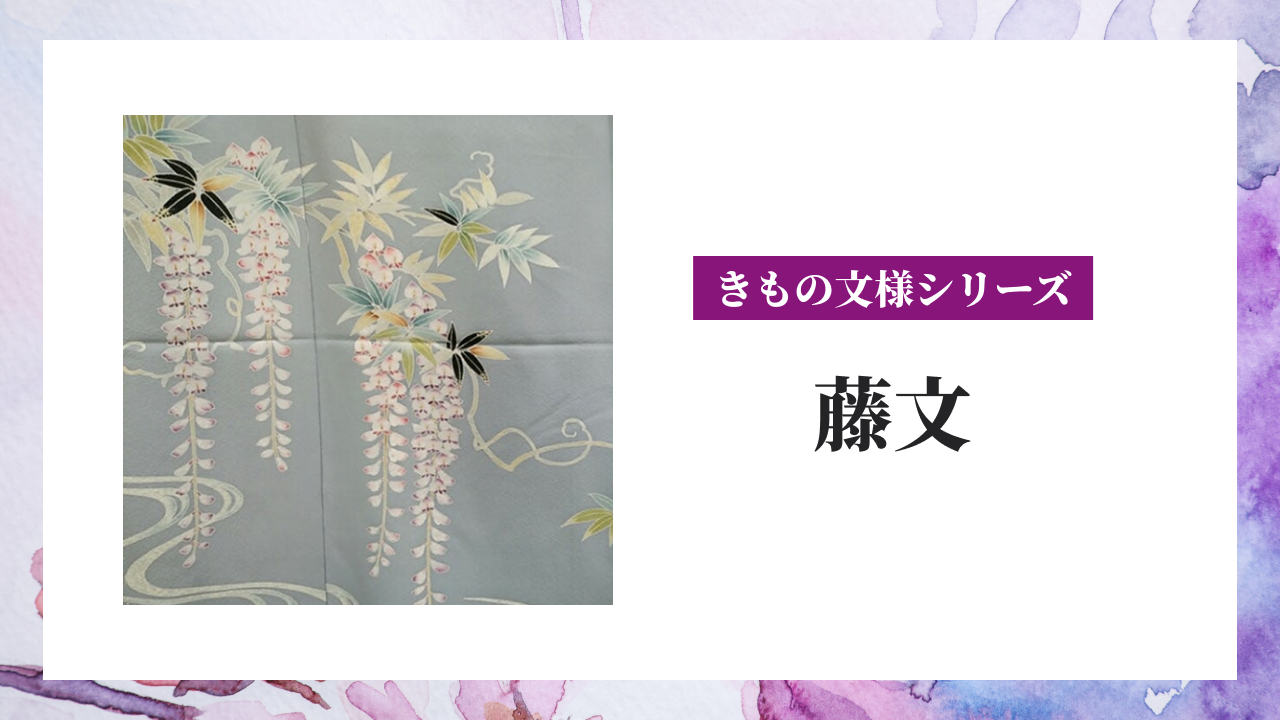最終更新日:
記事公開日:
【きもの文様シリーズ】麻の葉文

様々な着物の文様を求めて走り回っている「きもの文様 千文家」山下啓介です。
私が出会った文様と、関連する豆知識をご紹介します。
今日のきもの文様は『麻の葉文様』です。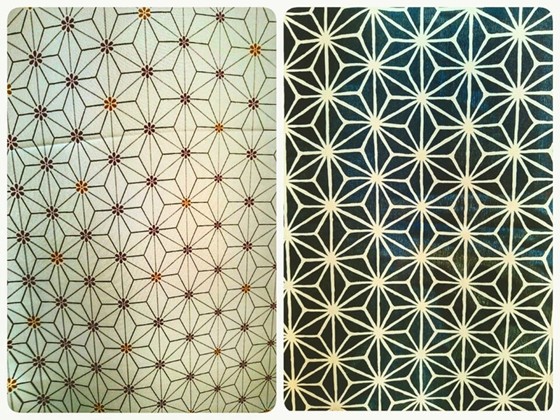
編麻の葉文様(あさのはもんよう)とは
正六角形を基調として水平・垂直・斜線によって構成された幾何学的な連続模様です。
その形が大麻の葉に似ていることから、この名が生まれたと伝えられています。
江戸中期の文政年間に歌舞伎役者の嵐璃寛(あらしりかん)が、大阪で“妹背門松”という芝居にて、娘役お染を演じた際、この文様を用いたことから、当時の京・大阪では麻の葉文を“お染形”と呼び好んだそうです。
麻は丈夫で真っ直ぐに早く成長することや、麻の葉模様そのものに邪気をはらう力があるとされたため、魔除けの意味もあります。

きもの、足袋、帯揚げに重ね衿など…代表的な和柄として様々なところで見かけますね。
健やかな成長を象徴することもあり、お宮参りの着物の長襦袢には『麻の葉文様』が多いんですよ!!
麻は神聖なもの
麻は日本の伝統文化や信仰から切り離せないもので、特に神道と古くから関わってきました。
絹などと共に、神に奉献する幣帛の一つであり、神事で使う罪科や穢れを祓う『はらえつもの』として、場を清めるために使われています。
成長の速さとたくましさに強い生命力を感じることに加え、白い繊維は神聖な物とされたのでしょう。
江戸時代になり、木綿が日本で生産されるようになっても「裃」などの礼服には麻を使用していたようです。
現在でもおなじみ、相撲の横綱が締める綱は白麻を使っています。
きもの以外でも、襖や屏風の裏張りなどの装飾、グラスなど…麻の葉文様、探してみると見つけることが多いんですよ~
意識すると身近なところから見つかるかもしれません。
ではでは、本日も最後まで読んで頂きありがとうございます。
記事提供:きもの文様 千文家_山下啓介
https://ameblo.jp/bonbonkeitan/entry-12249080228.html
ライター紹介