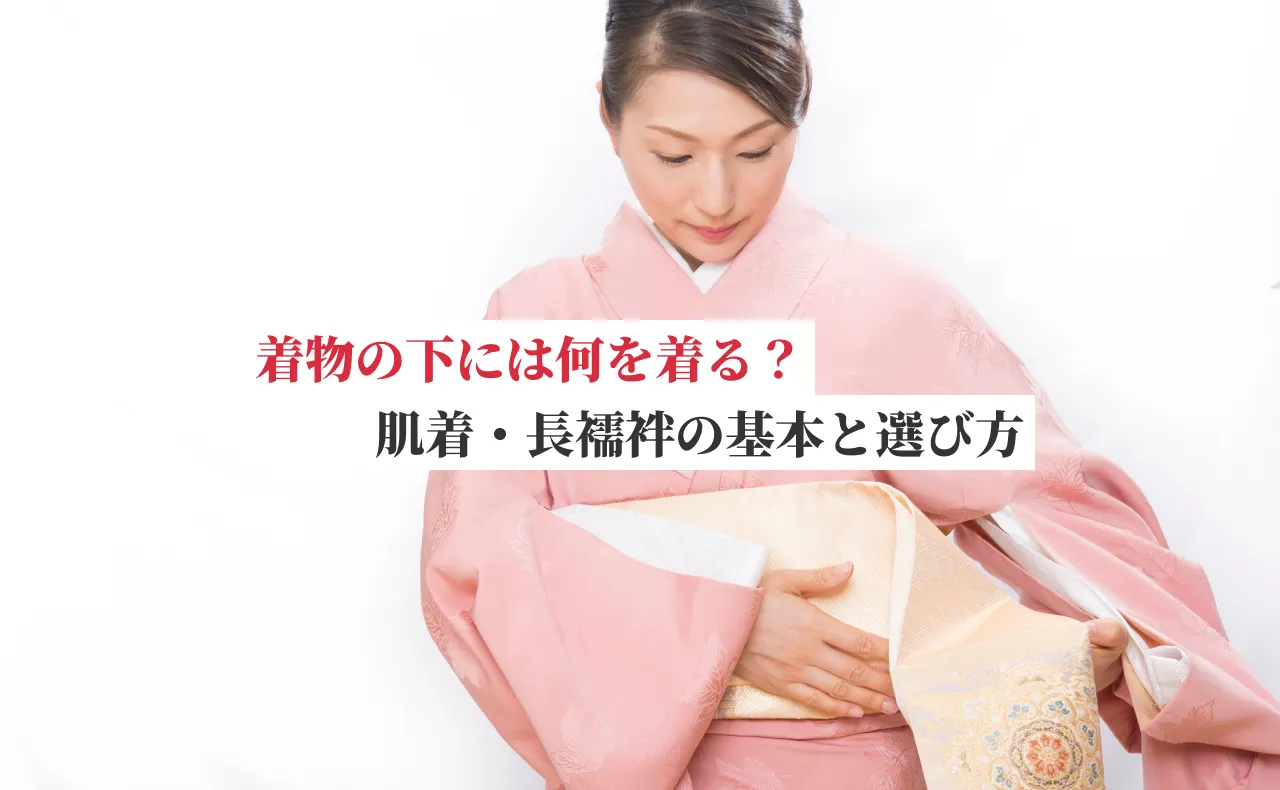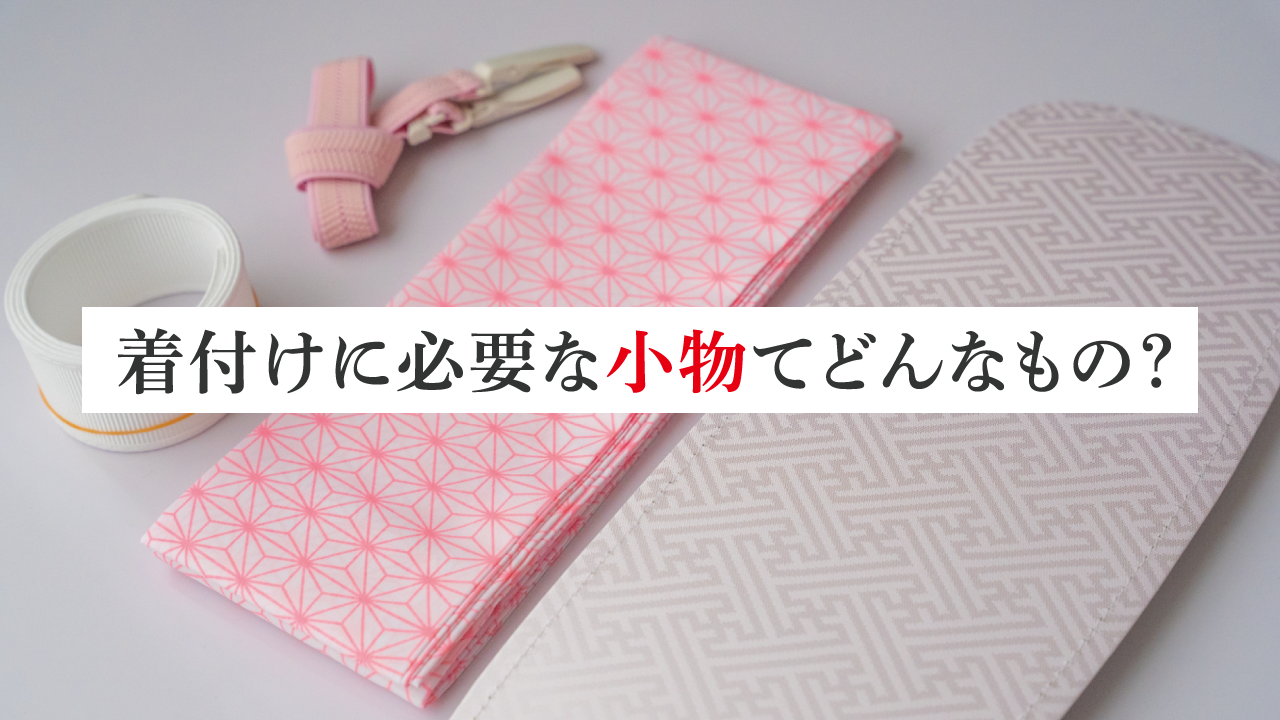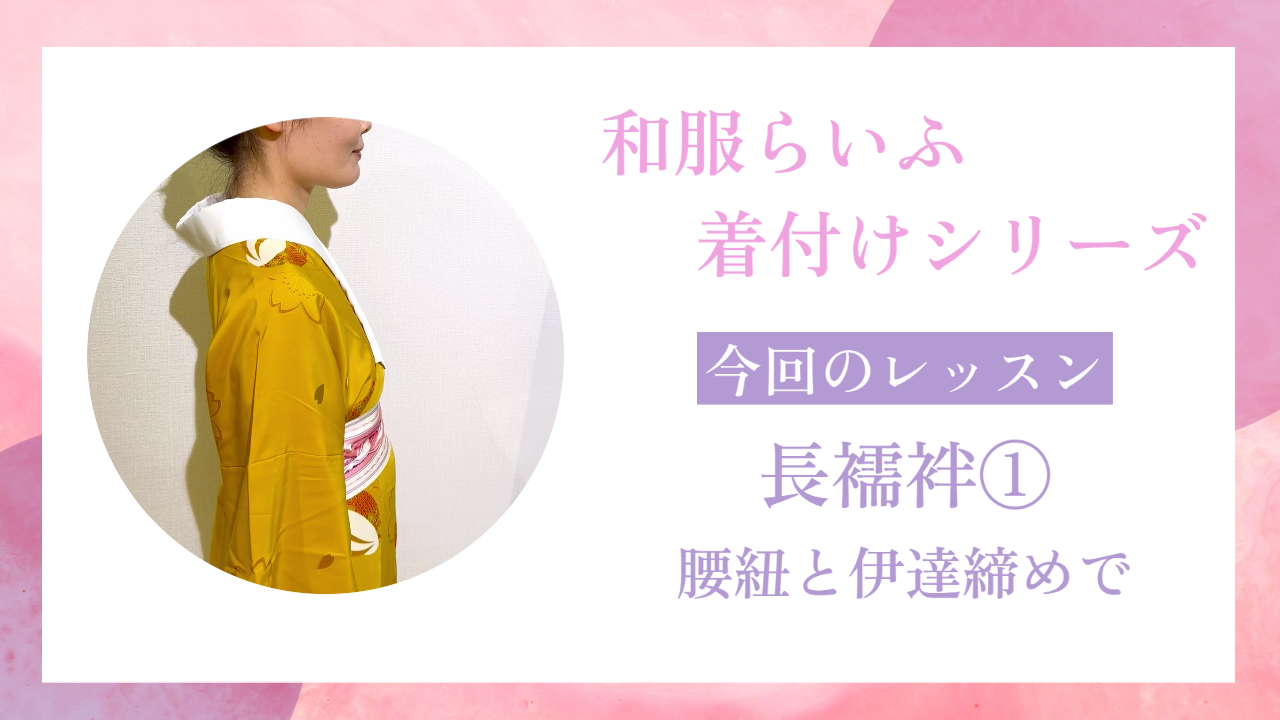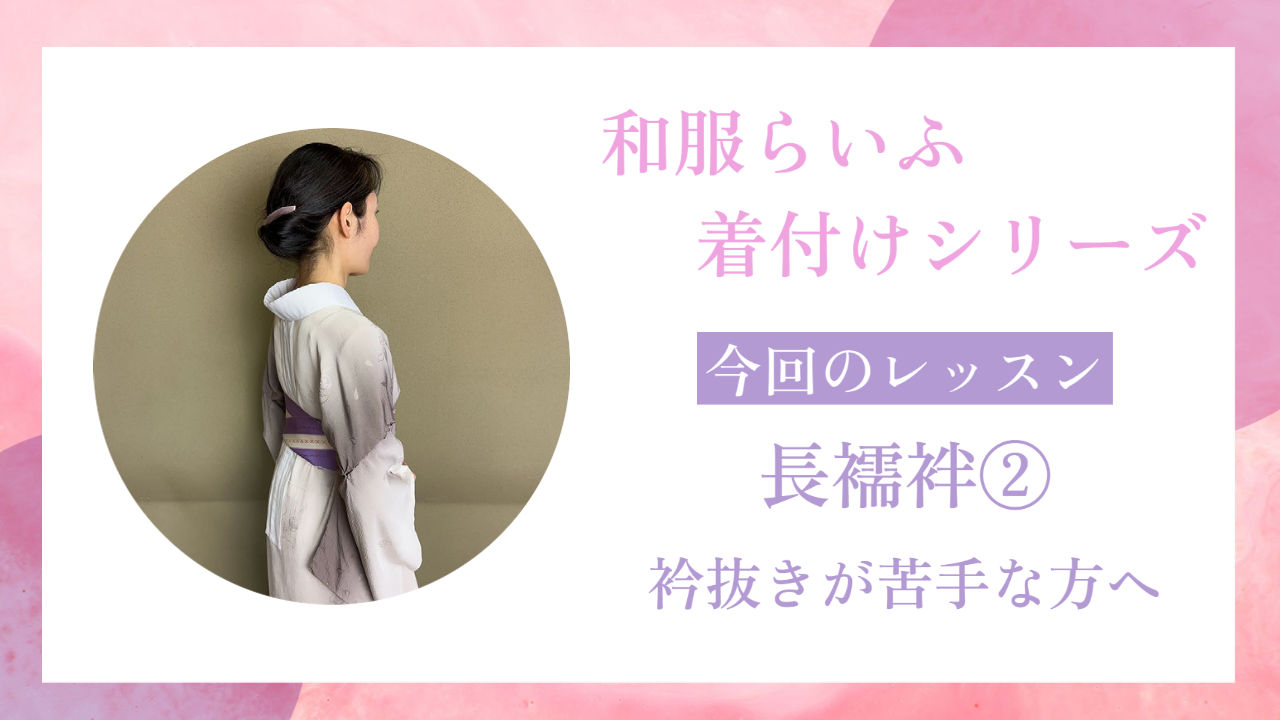最終更新日:
記事公開日:
【着付けシリーズ】名古屋帯の結び方:一重太鼓の基本

京都で着付け講師をしている中村笑子です。
Pointを分かりやすく解説しますので、ぜひ皆さんの着付けの参考にしてください。
今回のレッスン動画は名古屋帯で結ぶ『一重太鼓』です。
事前準備をしましょう
- 帯枕に帯揚げをかけて留めておきます。
- 仮紐1本、クリップ2つを使用します。
帯を巻きましょう
使用したのは一般的な名古屋帯仕立てと言われる帯です。
まずは半分に縫われている手先を身体に巻きます。
縫い目がある方が、袋帯でいうと耳側になりますので、縫い目が上、輪が下にして二周半巻きます。
しっかりと引き締め、帯を交差し、手先を前に持ってきてクリップで留めておきます。
ねじった根元をしっかりと引き締めて、三角の縫い目を裂かないよう気をつけながら開き、仮紐をします。
この時、柄が外側になるようにします。
帯枕を入れます。総柄の場合はあまり気にせずに帯枕を背中にのせても大丈夫です。
ワンポイントの柄がある場合はその部分がしっかりと出るように調整し確認してから枕を背中へのせます。
肘を開き、肘のバネと手首のスナップを一緒に使って、平らな方が背中側になるようにのせてください。
のせるときは枕の上下に気をつけてくださいね。
背中に帯枕をのせたら、帯揚げを脇まで外し、帯枕の紐を結びます。
お稽古では帯揚げは最後にしていきますが、お好みで先に結んでもOKです。
仮紐でお太鼓の形をつくっていきます。
二重太鼓の時と違い、名古屋帯でつくる一重太鼓は、背中にのっている帯は一枚のみです。
その一枚の帯と身体の間に仮紐をいれます。お太鼓の形をつくりたい位置を決めて、仮紐と帯を持ったら、紐より下のたれを折り上げ仮紐を前で結びます。
この時、紐の下線とお太鼓の下線をしっかりと合わせるとピシッとしたお太鼓になります。
たれ先の長さを確認したら、クリップで留めておいた手先をお太鼓の中に通します。
手先を通す位置は、仮紐が通っている位置と同じところです。折り上げたたれを巻き込まないように、手先をスライドするように引き抜きます。
手先が余るようでしたら、内側に折って長さを調節します。
手先と折り上げたお太鼓のたれをしっかりと押さえるように帯締めを締めます。
帯揚げも結んだら、最後の確認をして完成です!
※名古屋帯の方が簡単!と仰る方が多いような気がしますが、皆様はいかがでしょうか。
帯が長いとたれを折り上げるのが大変な場合もあり、私のお教室では苦手な方が多いんです。帯によって変わってきますので、色々な帯で結んでみてくださいね。
※お太鼓は帯の下線と同じ位置に合わせ、たれ先の長さはだいたい6㎝くらいの長さにしていただくと、良いと言われていますが、お好みやご身長、体系に合わせて形を決めてみてください。後ろ姿のバランスが取れます。
実際私は身長が160㎝以上ありますので、少し大きめのお太鼓にしています。
ライター紹介